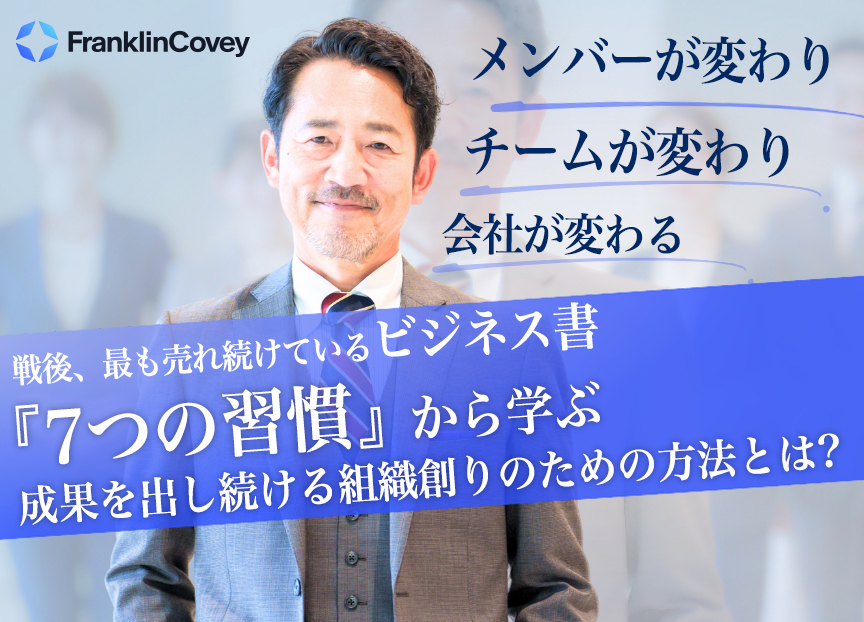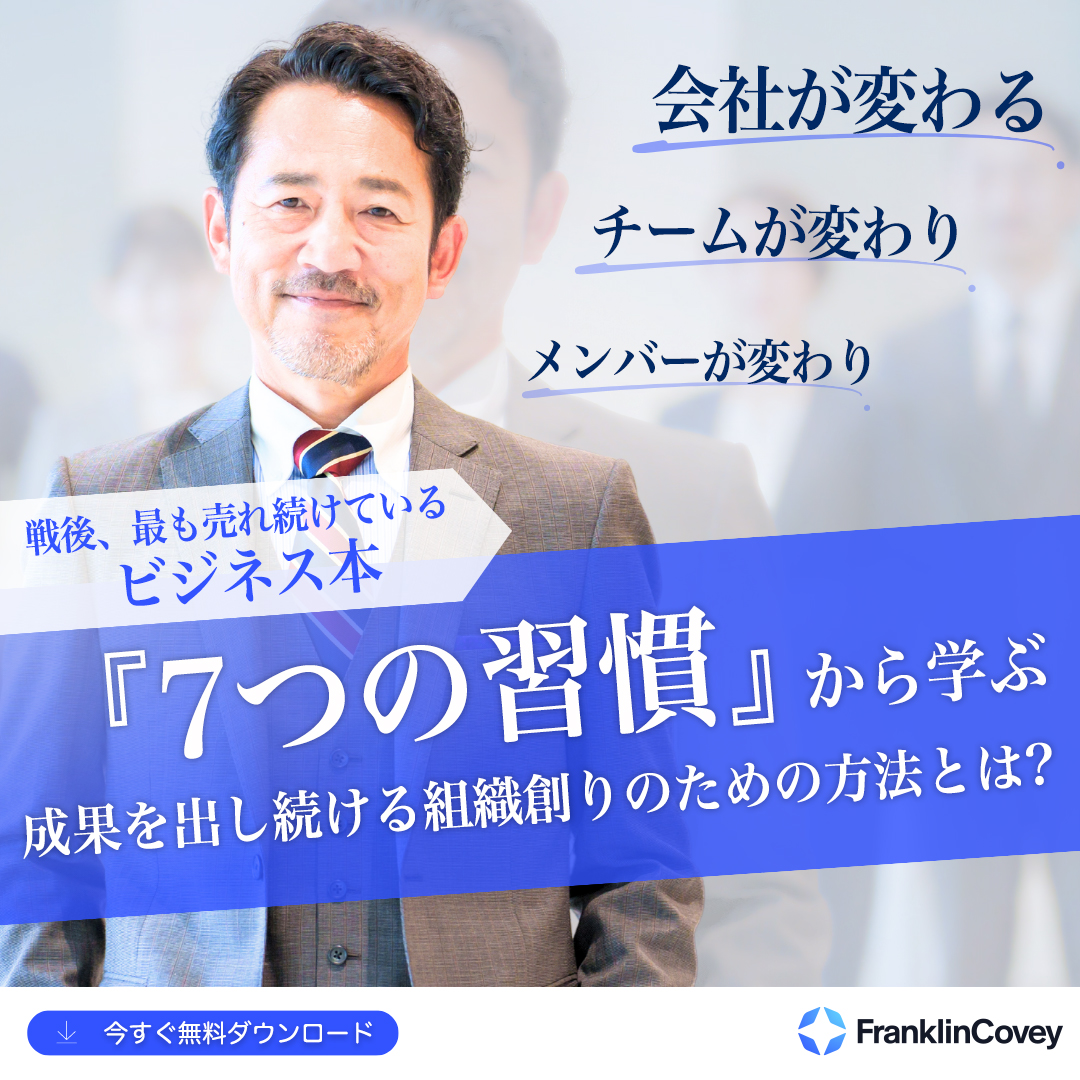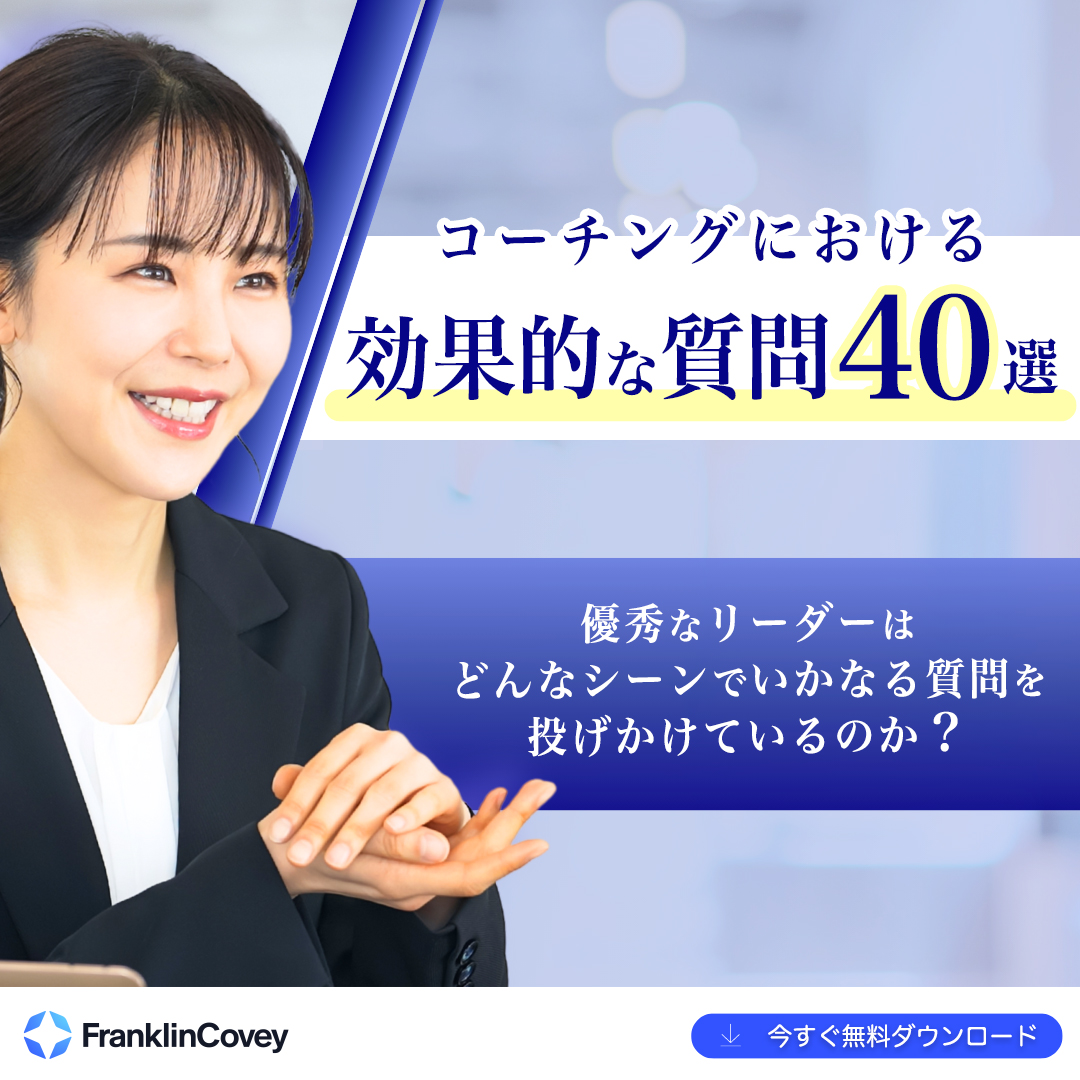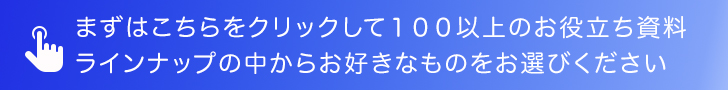ハイパフォーマーは常に高い目標に向かってチャレンジし続け、組織に大きな成果をもたらす貴重な存在です。組織の成長のためには、ハイパフォーマーの育成や既存従業員の底上げが欠かせません。
本記事では、組織の生産性を高めるハイパフォーマーに共通するスキル特性や分析方法について詳しく解説します。ハイパフォーマーの育成方法や離職を防ぐポイントも紹介するので、企業の採用や人材開発のご担当者はぜひチェックしてください。
ハイパフォーマーは組織の成長に貢献する人材

ハイパフォーマーとは、企業の業績に大きく貢献する高い成果を継続的に上げる人材を指します。ハイパフォーマーの生み出す成果は組織の成長や売上に大きく関わるため、企業にとって欠かせない存在です。
ハイパフォーマーが重要な理由
労働力不足が顕在化し、限られたリソースで最大の成果を生み出す必要がある現代において、常に高い目標にコミットし続けるハイパフォーマーの存在は非常に貴重です。組織におけるハイパフォーマーの人数や質を向上することは、組織の成長にダイレクトに影響するといえるでしょう。
また、ハイパフォーマーは成果を出すだけでなく、組織やチーム全体にポジティブな影響をもたらしてくれます。彼らの存在は組織の継続的な成長を支える原動力となるほか、組織の競争力を高める役割も果たします。
ハイパフォーマーが組織にもたらす効果
組織にハイパフォーマーが存在することで、さまざまな好影響がもたらされます。組織の業績や利益にダイレクトに影響するだけでなく、チーム内の意識改革や業務効率化、さらには従業員全体のヒューマンスキル(人格力)の底上げも可能です。
ハイパフォーマ-の基礎をなすヒューマンスキル
ハイパフォーマーに共通する「主体性」「問題解決能力」「自己管理力」などの特性は、いずれもヒューマンスキル(人格力)の土台の上に成り立っています。たとえば、自己認識力が高い人ほど、自分の感情や思考のクセを客観的に捉え、安定した行動を取ることができます。また、他者との信頼関係を築くには、共感力や傾聴力といった対人スキルが不可欠です。
ヒューマンスキル向上が組織全体に与える波及効果
ハイパフォーマーが高いヒューマンスキルを実践する姿は、周囲のメンバーにとってよいモデルとなります。結果として、組織全体のコミュニケーションの質や協働意識が向上し、ヒューマンスキルの底上げが図られます。
ローパフォーマーとの違い
組織には、ハイパフォーマーと対極の性質を持つ「ローパフォーマー」も存在します。ローパフォーマーは常に受動的で上司からの指示がないと動けず、業務の成果も低水準な従業員を指します。
ハイパフォーマーは主体的に行動し、課題を改善しながら成果を出す一方、ローパフォーマーは組織の成長になかなか貢献できません。成長意欲が少なく、現状維持に甘んじやすいため、組織やチームにネガティブな影響を与える場合もあります。
ハイパフォーマーに共通する特徴

ハイパフォーマーといわれる人材には、いくつかの共通項がみられます。ここからは、ハイパフォーマーに共通する行動特性を紹介します。
期待以上の成果を発揮する
ハイパフォーマーは、上司や顧客の期待を上回る成果を継続的に発揮します。結果にこだわる姿勢が強く、常に目標達成に向かって行動し続けることができます。
また、目先の業務の優先順位を的確に判断できるほか、問題解決能力にも優れているのが特徴です。そのため、周囲からの信頼や人望を集めやすいといえます。
チャレンジ精神や行動力に長けている
ハイパフォーマーは、困難な課題に対しても積極的に挑戦する姿勢を持っています。失敗や逆境を恐れず自ら行動を起こすことで、大きな成果を得ることができるでしょう。
たとえ失敗したとしても、ハイパフォーマーは次の挑戦への糧にする前向きな姿勢も持ち合わせています。与えられた環境や現状に満足せず、常に新しい価値を生み出そうとする姿勢は、組織内で高く評価される点の1つです。
ヒューマンスキルやコミュニケーション能力が高い
ハイパフォーマーは、ビジネススキルの基本であるコミュニケーション能力にも秀でています。
単に話す力だけでなく、相手の意図を正確に理解する傾聴力や相手の立場や場面に応じて適切な言葉遣いやアプローチを選択し、効果的に意思を伝える能力など、マネジメント層に求められるヒューマンスキル(人格力)を持ち合わせているのが特徴です。
上司や同僚との意思疎通を円滑に行い、組織内の良好な人間関係を構築することで、組織の目標達成に大きく貢献します。
常に自己研鑽をしている
成果を出し続けるハイパフォーマーは、常にスキルアップのための自己研鑽を欠かしません。現状のスキルや知識量に満足することなく、さらに高みを目指すために学び続ける姿勢を持っています。
また、技術スキルだけでなく、対人関係能力や自己管理能力など、ヒューマンスキル(人格力)の向上にも意識的に取り組んでいます。
さらに、業務時間外や休日に読書・セミナー受講・資格勉強などを行い、新たなスキルの取得に向けて努力し続けているのも特徴の1つです。
ポジティブ思考である
ハイパフォーマーは、困難な状況に陥ったときでも前向きな姿勢を持ち続けます。問題に直面した際も自分自身が成長するチャンスととらえ、積極的に行動を起こします。
ハイパフォーマーのポジティブなマインドは、組織やチーム全体にも活力をもたらしてくれるでしょう。周囲のネガティブな空気に流されず、常に自分軸を持ち続けられるのも特徴の1つです。
公私の区別と自己管理を徹底している
ハイパフォーマーは仕事とプライベートの線引きをはっきりと設けており、的確なワークライフバランスを保ち続けます。
体調にも気を遣い、集中すべきときに最大限の力を発揮できるよう、常に準備を怠りません。時間管理や自己管理を徹底することで、高い生産性を維持し続けています。
ハイパフォーマー採用・育成のための分析方法

優れた人材を採用・育成するためには、求める人物像や行動特性を明確にしておく必要があります。
1.ハイパフォーマーの定義・求める成果を明確にする
まずは、自社にとってのハイパフォーマー像を定義しましょう。期待する成果・求める行動基準・必要な能力を職種ごとに明文化することで、評価基準が明確になります。
このように、組織で活躍するハイパフォーマーを採用・育成するためには、目指すべき人物像を具体的に分析することが重要です。
2.自社におけるハイパフォーマーを選定する
ハイパフォーマーの定義を明確にしたら、既存の従業員のなかからハイパフォーマーに相当する人材を選定しましょう。選定軸にブレが生じないように客観的な評価や数字を参照し、従業員の上位2割程度を選定するのが一般的です。
3.選定したハイパフォーマーの行動特性・資質を分析する
続いて、選定したハイパフォーマーの行動特性・思考パターン・価値観などの分析を行います。実際に成果を上げている人材をサンプルにすることで、自社で活躍する人材の共通点が明らかになるでしょう。
どのような人材が自社で活躍しやすいのかを把握しておくことで、採用面接で同様の成果を上げられそうな人物を選定しやすくなります。
4.分析結果を採用条件や研修内容に落とし込む
最後に、これまでの流れで得られた分析結果を、今後の採用条件や研修内容に落とし込みましょう。
たとえば、選考時の評価項目に具体的な行動特性を設けたり、社内の研修プログラムをハイパフォーマーの成長要因に沿って構成したりすることが可能です。分析結果をより具体的に反映することで、成果に直結する人材を生み出しやすくなります。
ハイパフォーマーの離職を防ぐためのポイント
ハイパフォーマーは能力が高いゆえに、現在勤めている企業から転職するチャンスが多いと考えられます。能力に自信のあるハイパフォーマーを抱える企業は、常に離職の可能性と隣り合わせといえるでしょう。
優秀な人材の流出を防ぐには、働きやすい環境と正当な評価を提供することが必要です。
評価制度を整備する
ハイパフォーマーの離職を防ぐには、成果とプロセスの双方を適切に評価する制度の整備が必要不可欠です。日々の努力やもたらした成果を正当に評価することで、ハイパフォーマーのモチベーションを維持させることができます。
適切な評価を行うためにも、業務のフィードバックや1on1などを定期的に行い、日頃から意思疎通を図ることが重要です。また、評価をしっかりと給与や賞与に反映することも欠かせません。
業務量を調整する
ハイパフォーマーは業務遂行能力が高いゆえにほかの従業員よりも多くの仕事を任されやすく、気付かぬうちに業務過多になりがちです。
成果を出す力があるからこそ、適切な業務配分とリソースの確保を行う必要があります。過重労働はパフォーマンスの低下や離職のリスクにつながるため、常に業務量の調整管理を行いましょう。
適切な裁量を与える
優秀な人材には、業務の進め方や意思決定において一定の裁量を与えることが重要です。上層部の指示を待つのではなく、自ら考えて行動できる環境を作ることで、ハイパフォーマーのさらなる成長意欲や責任感を引き出せるでしょう。
過度な管理や業務における制約はモチベーションを削ぐ原因となるため、信頼をもって任せる姿勢が大切です。
定期的な面談を行う

ハイパフォーマーの離職を防止するためには、定期的な面談を行うことも効果的です。面談は現状の課題や将来のキャリア志向を確認する貴重な機会となり、日々の業務の忙しさで見落としがちな悩みや不満も早期に把握できます。
双方向のコミュニケーションによって上層部との信頼関係を構築することで、離職のリスクを低減できるでしょう。
ローパフォーマーのパフォーマンスを向上させる
組織にはハイパフォーマーと平均的な従業員のほかに、成果を上げにくいローパフォーマーも存在します。組織に大きな成果をもたらしているハイパフォーマーにとって、ローパフォーマーの存在は快いものではないでしょう。
組織全体のバランスを保つためには、ローパフォーマーのパフォーマンスや成果を向上させることも欠かせません。
まとめ

常に高い成果を上げ続け、組織にポジティブな影響を与えてくれるハイパフォーマーは、企業にとって欠かせない人材です。組織のダイバーシティ化やAIが台頭している昨今、ハイパフォーマーにはこれまで以上にヒューマンスキル(人格力)が求められているといえるでしょう。フランクリン・コヴィー・ジャパンが提供する人材育成プログラム「7つの習慣」は主体性、信頼構築、効果的なコミュニケーションなどのスキルを磨くことを通して、ハイパフォーマーの育成を後押しします。
最高の業績を上げている組織は、常に以下の4つの点を適切に実施しています。
・各階層で優れたリーダーを育成する
・個々人に効果的な習慣を形成する
・包括的で信頼性の高い文化を構築する
・共通の実行システムにより最重要目標を追求する
フランクリン・コヴィーは、上記の4つの重要領域における組織の行動変容の実現を通して「お客様の成功」に貢献するサービス提供や支援をしています。人材育成や、組織風土の醸成や変革などご検討されている方はこちらよりお気軽に問い合わせください。